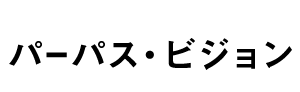- TOP
- メディア
- ALCONIX's BluePrint
- 海岸を守る、未来を創る ~海岸清掃で築く企業の絆~
海岸を守る、未来を創る ~海岸清掃で築く企業の絆~

皆さん、こんにちは!アルコニックスIR広報部のSです。
今回は、私も参加した新卒1~3年目社員とグループ会社の株式会社富士根産業の若手社員と一緒に静岡県沼津市の片浜海岸で行った「海岸清掃活動」についてご紹介します。
非鉄金属という貴重な地球資源を取扱う当社グループは、環境問題を経営上の重要課題の一つと捉え、グループ全体でサステナビリティ活動やSDGs推進に積極的に取り組んでいます。今回の活動はSDSs推進の一環として、環境問題に向き合いながら、地域社会に貢献し、さらにグループの若手社員同士の交流を深めることを目的として実施されました。
具体的な取組みをご紹介するとともに、皆さまが環境問題へ取り組むきっかけになると嬉しいです。
アルコニックスがグループを挙げて地球環境問題に取組む理由
なぜ、アルコニックスがグループを挙げてこのような実地活動を行うのか。
それはサステナビリティや地域社会への貢献活動を「自分ごと」として社員一人ひとりが認識し、次の行動へ促すためでもあります。会社として積極的にサステナビリティ活動に取組むことも重要ですが、私たちそれぞれが日常生活で意識を高め、行動に移すことがSDGsの推進、地球環境問題の改善に繋がる、と社会活動を行う企業として信じています。
さらに、今回の研修と海岸清掃活動には、大きな3つの目的があります。
- 地域貢献活動の一環
私たちは、全国にあるグループ会社ごとに地域社会に貢献する活動を進めています。今回はその第一弾として、静岡県沼津市の片浜海岸で清掃活動を行いました。片浜海岸からは、雄大な富士山を望むこともでき、その環境を守ることは、地域の未来を守ることにも繋がります。
- 若手社員へのサステナビリティ研修
環境問題について学び、実際に行動することで、社員一人ひとりがサステナビリティを「自分ごと」として捉え、グループ内におけるSDGs推進意識の醸成を目指しました。普段の業務や生活の中で持続可能な行動を実践するきっかけとなることを期待しています。
- グループ内の交流
普段は離れた場所の別々の会社で働いている若手社員が、部門や会社の枠を越えて、同じ目標に向かって協力することで、グループ全体のつながりを深め、お互いについて知る良い機会となることを目指します。
今回の活動を企画した当社の担当者は、
「海洋プラスチックを含めて、定期的に様々な研修動画を社員に発信していますが、それだけに頼っていては『自分ごと』として捉えることが難しいと考えて今回の活動を企画しました。今回の活動を通じグループの一体感を高めていきたい、という狙いもありました。」
と語っています。
私たちは、個人としても企業としても、環境を守るための具体的な行動が求められており、このように実際に自分たちが活動に加わることで「自分たちにできること」を考えるきっかけを得ることができました。
百聞は一見に如かず、ということわざもあるように、あなたも、実際に体験することで得られる学びの大きさを感じたことがあるのではないでしょうか。
海洋プラスチック問題ってどんな問題?
「海洋プラスチック問題」という言葉を最近よく聞くかもしれませんが、具体的にどんな問題かご存じでしょうか。
海洋プラスチックとは、ゴミとなって海に流出するプラスチックのことです。海には、なんと1億5,000万トンもの海洋プラスチックが漂っていると言われています。そして、毎年800万トン以上のプラスチックが新たに海に流れ込んでいるんです。
800万トンと聞くと大きすぎてピンとこないかもしれませんが、毎分15トン、毎秒250kgが流出していると聞くと、なんとなく想像できると思います。
しかも2050年には魚よりプラスチックごみの量が多い海になることが予測されています。驚きですよね!
そして、このプラスチックごみは、海の生き物たちに大きな影響を与えています。例えば、ウミガメがビニール袋をクラゲと間違えて食べてしまったり、魚の体内に小さなプラスチック(マイクロプラスチック)が溜まってしまったり…。その魚を私たちが食べることで、間接的に人間にも影響が及ぶ可能性があるんです。
アルコニックスグループはプラスチックを取扱う会社ではありませんが、海洋プラスチック問題は緊急で取組む必要がある重要な課題の一つであると捉え、解決に向けて行動しています。後ほどその一例をご紹介します。
海洋プラスチック問題と私たちにできること
実際に海岸へ行って活動する前に、静岡県廃棄物リサイクル課より高柳様を講師に迎え、「海洋プラスチックごみ問題について」の講義を行っていただきました。海洋プラスチックが環境や生き物にどのような影響を与えるのか、静岡県の海岸には実際にどのようなゴミが漂着しているのかなどをご説明いただきました。
講師の高柳様からも
「まずは、皆さんに海洋プラスチックごみ問題をはじめとした環境問題について知ってもらいたいです。そして現状を知ったうえで、課題解決に向けた行動を実践し、事業活動全体におけるプラスチックの使用量削減の取組みを促進していただくことを期待しています。」
とメッセージを頂きました。


参加者からは、
- 「プラスチック問題が他人事ではなく、より身近なものと感じるようになった」
- 「身近なできることから取り組むことが、将来の地球を守ることに繋がるんだと感じた」
- 「私に実践できるサステナビリティにつながる取組みは何かということを考える良い機会となった」
など、今まで自分自身とは直接関係がない、漠然とした問題だと感じていたものが、講義を受ける中で、実はとても身近な問題で、一人ひとりの小さな取組みが大切だということに気づくきっかけになったという声が多く寄せられました。
6R県民運動についても、静岡県の取組みを知る良い機会になりました。私も、普段からマイボトルを持ち歩くだけではなく、コンビニでレジ袋やプラスチック製スプーン、ストローをできるだけ断るようになり、自分の意識が変わったと感じています。
あなたも、まずはRefuse(断る)から始めてみませんか?
Waterlogicで廃プラ削減に挑む
続いて、当社事業戦略部の宮城さんによる「水道直結型ウォーターサーバーとSDGs」について講義が行われました。
日本にいるとなかなか気づくことが難しいですが、普段何気なく飲んでいる水が、実は世界中で大きな問題となっていることをご存じですか。
海岸に漂着したプラスチックごみの約40%は飲料用ボトルと言われています。そのため、世界でも飲料用ボトルの使用制限など議論が始まっており、日本でもマイボトルを使用する人が増えてきています。
そんな中で、注目されているのが「水道直結型ウォーターサーバー」です。
会社やご自宅でウォーターサーバーを利用する方が多いと思いますが、ほとんどのウォーターサーバーはボトリングされた水を交換する必要があり、ボトルの配達、ボトルの処理・リサイクルが必要になります。水道直結型ウォーターサーバーは水道と直接つながっており、水道水をろ過し、ボトルレスで安全でおいしい水を提供できるものです。
当社が取扱う「Waterlogic」は、まさに水道直結型ウォーターサーバーの1つで、特殊な浄化技術、ろ過システムで細菌やバクテリアなどを除去することができる製品です。廃プラ削減やPFAS(有機フッ素化合物)問題を含む安全な水の確保などの社会問題の解決に貢献しています。
さらに宮城さんは
「地域に無料給水スポットとしてWaterlogicを設置すれば、地域のペットボトルの消費や廃棄の量を削減することができ、地域全体での啓蒙にも繋がる」
と語っています。
講義を聞いた参加者からは、こんな感想が寄せられました。
- マイボトルを使用するといった小さなことがサステナビリティにつながることに気づくことができた。
- 自分の会社の事業がペットボトルの削減に役立っているのは誇らしいと思った。個人の取組みももちろん重要だが、ビジネスと社会貢献が両立できる仕組みは今後も必要だと感じた。
海岸清掃活動の成果
午後からは、片浜海岸に移動し、実際に海岸清掃を行いました。みなさん、海岸にどのくらいゴミが落ちているか想像できますか?一見綺麗そうにみえる海岸でも実際に行ってみると、思った以上に多くのゴミが落ちていました。特に、ペットボトルや食品包装材などのプラスチックごみが多く見られ、海洋プラスチック問題の深刻さを改めて実感できました。

活動の結果、1時間ほどで合計 約130kg ものごみを回収することができました!
- 「多くのプラスチックごみが海岸に漂着しているのを目の当たりにし、その量に圧倒された」
- 「実際にゴミが散乱している海岸を見て初めて、どこか遠くで起こっているように感じていたこの問題が現実味を帯びてきて自分事に捉えられた気がした」
という声が多く聞かれ、実際に海岸を訪れて、経験したからこその感想が寄せられました。
特に、外国語表記のごみよりも、国内から流出した日本語表記のゴミの方が多いことを実際に感じて、「自分たちの生活が直接関係している」と気づいた社員も多かったようです。

今回一緒に参加した富士根産業の八木さん(総務部長)は、
「実際に海岸清掃をたった1時間やっただけでも、非常に沢山のペットボトルや、プラスチック容器が散乱しているのを目の当たりにし、ペットボトルを使わない、即ちマイボトルをもっと積極的かつ当たり前のように日々利用すべきであることを強く認識しました。今回は共同で海岸清掃活動を行いましたが、これを機に年に数回、当社単独でも海岸清掃活動を行いたいと考えています。」
と今回の研修と活動によって意識が変容した旨を語っています。

今後の展望
今回の研修と海岸清掃活動を通して、私たちは「環境問題は自分たちの生活とも深くかかわっているんだ」ということを改めて実感しました。
そして、グループ内の繋がりも深まり、これからも共に手を取り合って取り組んでいこうという気持ちが一層強くなりました。また、自分たちの行動が、地域全体の行動や意識を変えるきっかけになるかもしれないと思うと、非常に大きな経験ができたと感じます。
これからも、アルコニックスはグループ会社と連携して、グループ全体で環境保全や地域貢献活動を続けていきます。そして、社員一人ひとりが自分にできることを考え、「自分ごととしてのSDGs」を行動に移せるような機会を増やしていきたいと思っています。
また、Waterlogicをはじめとする廃プラ削減プロジェクトをさらに発展させていくと同時に、今回の研修で得た学びを活かして、より効果的な活動を展開していく予定です。
いかがでしたでしょうか。今回はアルコニックスグループの地域社会への貢献、SDGs推進の一環である海岸清掃活動を紹介しました。この記事を読んでいるあなたも、まずは身近なところから始めてみませんか。例えば、マイボトルを持つ、レジ袋を断ってマイバッグを使用する、地域の清掃活動に参加する…。小さな一歩が、未来の地球を守る大きな力になります。
私たちと一緒に、未来のために行動してみませんか?
 ・空調機器部品(タンク・配管)の製造加工、コンプレッサー部品(シリンダー・ベアリング)の切削加工、ユニット組立などを行っています。
・空調機器部品(タンク・配管)の製造加工、コンプレッサー部品(シリンダー・ベアリング)の切削加工、ユニット組立などを行っています。
・SDGs推進にも積極的で、令和6年度に「沼津市SDGs推進パートナー」として登録されました。