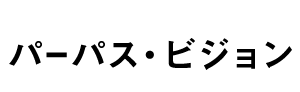- TOP
- メディア
- ALCONIX's BluePrint
- ビジネスの未来を担う、アルコニックスグループのCVC
ビジネスの未来を担う、アルコニックスグループのCVC

アルコニックスグループは、スタートアップ企業への出資を目的としたコーポレートベンチャーキャピタルファンドの運営のため、2021年8月にアルコニックスベンチャーズを設立。グループの持つグローバルネットワークや商社・製造業の知見を活かし、新たなシナジー創出を目指しています。
単なる投資にとどまらず、未来へつなげるビジネスを産み出すCVCの活動について、アルコニックス・執行役員の木山さんにお話を伺いました。
”やってみなはれ“の精神でCVCを設立
CVC設立時にアルコニックスグループが抱えていた課題として、まだマーケットに出てきていない先端的な商材を開拓し取り扱うことで、他社と差別化を図っていく必要がありました。
アルコニックスグループは素材の調達と提供、モノづくりの領域で事業を展開していますが、例えば素材に関して言うと、新しい特性や機能をもった素材が世の中にどんどん出てくる。そのすべてにヤマを張ることはできませんが、どこかに張っておかないとビジネスチャンスを逃してしまう。
M&Aや合弁会社の設立も手段のひとつですが、まだ世の中に採用実績すらない、新規性の高い素材や技術を産み出しているスタートアップに対して、投資という一歩踏み込んだ取組みを考えた際、当時のアルコニックスの投資判断・意思決定の仕組みではスタートアップの資金調達のスピード感に間に合わないという実態がありました。
そこで、機動性を持って取組みを行うために、2021年8月にCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)※を立ち上げました。アルコニックスベンチャーズという別会社を設立、同社が無限責任組合員としてファンドを設立、運営をしています。
ファンドでは投資委員会を組成し意思決定をしているため、非常にシンプルな体制でスピード感を持った投資判断を行えています。
できるだけリスクはつぶして投資判断・意思決定をしていますが、スタートアップへの投資は失敗する可能性もある。しかし、リスクだけを考えているとビジネスチャンスを逃してしまうかもしれない。
ファンド設立時に「要は“やってみなはれ”ということですよね」と取締役会で言われた言葉が印象に残っていて。リスクを取って未来のビジネスをつかみに行く、まさにそれはビジネスの本質だなと感じました。
※事業会社がスタートアップ企業に投資し、戦略的支援を行う手法の一つ

CVCの活動から生まれる新たなビジネス
一般的にベンチャーキャピタルは “純投資”によるリターンを目的としていますが、アルコニックスのように事業会社が運営するCVCでは、出資を通じて自社事業の収益に貢献する新たなビジネスを創出することも重要な目的です。
そのため、CVCの活動を担う事業戦略部と営業部門の各部署が連携し、投資先候補のリストアップや情報共有、また投資を実行した投資先についてはマーケティング、営業支援までを協働してサポートする体制(通称:Team Catapult)を構築しています。
製品自体の可能性や売り方など営業部門の意見も聞いた上で投資判断を行っています。
アルコニックスが投資先スタートアップの営業をサポートしその商品が売れるようになると、スタートアップ自体のバリュー(企業価値)が上がります。それにより投資収益を得られるのはもちろんですが、アルコニックスとしてビジネスの収益も上がるというシナジーを生み出せているのは、ファンドを運用する前から営業部門の巻き込みを進めていたからこそ。
今後は、グループ会社にも参画してもらい、これまで以上にアルコニックスグループ全体で付加価値向上を追求していきたいです。
グループ企業を武器に、製造業への投資も強化していきたい
CVCの投資領域としては、アルコニックスグループの事業領域と親和性の高い、素材とモノづくりを中心に投資を行っています。
今現在は運用額の40%弱の金額で10件の投資を行っており、そのうち6件が素材に関連した事業を行うスタートアップです。(例:名城ナノカーボンやノベルクリスタルテクノロジーなど)
今は、モノづくり領域への投資比率を更に増やすべく考えており、検査業界等に注目しています。たとえば、車のドアノブのような部品は製造過程で、プラスチックにニッケルをメッキしたりするんですね。1日何千個も製造されるのですが、その製品を出荷する前に人の手と目で全数検査しています。
とても人手がかかっているのですが、今後、国内が人手不足になっていくにつれて、検査を行う人材を教育することや雇用することすら難しくなってくることが想定されます。その時、例えばAIなどを用いてその検査の部分を自動化できたら課題の解決につながりますよね。
ただ、落とし穴もあって、AIだと判断が正確すぎるがゆえにNGとOKの線引きが非常に難しいんです。曖昧さを許容できたり、不必要な検知を排除出来たり、まだ人の目による判断が上回ることもあります。
当社はグループ企業に製造業もあるので、スタートアップの技術を持ってグループ企業の困りごとを解決することで生産性が上がり、(検査の事例でいうと)どこまでだったら許容できるかを研究することもできる。
さらに、そういったソリューションを自社の商材として取り扱うことで、これまでのアルコニックスとは違うビジネスも展開できる可能性もあります。
素材はもちろんですが、モノづくり関連のスタートアップへの投資も増やしていきたいと考えています。
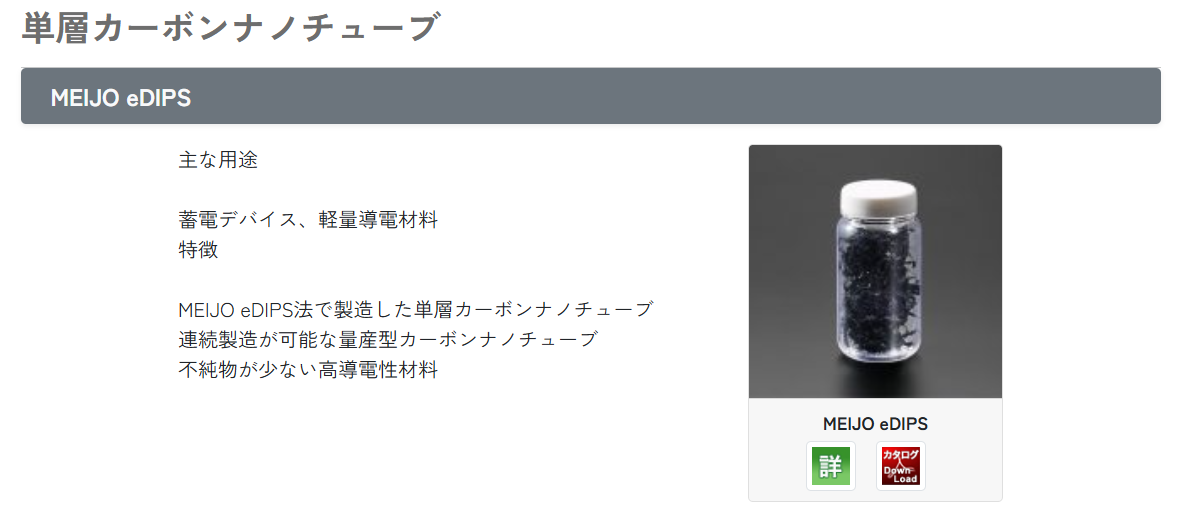
投資先の名城ナノカーボンが製造する「単層カーボンナノチューブ」
スタートアップとの協業が人材育成につながる
スタートアップへの投資は、キャピタルゲインやビジネスへの直接的な効果だけにとどまりません。具体的には、若手メンバーが投資先スタートアップに携わることで、スピード感のある成長と“ゼロからイチ”を創り出すそのプロセスを目の前で体験できることです。
マーケティングの手法や製造拠点の選定、資金調達、さらには経営判断にいたるまで「事業をどのように進めていくのか」を目の前で見ることは、日々の営業業務とはまた違う刺激にもなっていると思います。
時には想定通りに進まないこともありますが、それもよい経験となっています。
リソースが限られているスタートアップ側にとっても、アルコニックスの製品・市場情報力やマーケティング力、海外マーケットへの拡大展開力などに魅力を感じて出資を受け入れていただくことが多いです。
他にも、グループ会社に製造企業があるので、製造協力や製造請負もできる。そうなると、当社にとってもグループ会社の資源活用につながり、稼働率の向上といった効果も期待できます。

TeamCatapultのメンバー
社会課題に応える技術を、CVCを通じて支援
CVCで投資をするスタートアップは、先端技術や新しい取り組みをしている企業ばかりです。人手不足や高齢化などの社会課題に対して向き合い、課題解決をすることで“便利さ”を提供し、「どこかにいる、誰かの未来のため」に皆さんの生活が豊かになることを目指している。
アルコニックスグループは投資やビジネス取り組みを通じて、新しい素材とモノづくりの社会実装のサポートを行っていくことで、価値を提供していきたいと思っています。
まとめ
スタートアップへの投資を通じて、未来のビジネスチャンスが生まれ、新たな価値創造を実現するCVC。
長期経営計画2030で新たな「勝ち筋」や「ソリューション」の発掘が掲げられていましたが、CVCの活動が担っていく部分も大きいのではないでしょうか。木山さんが見ている景色の中にはスタートアップの活躍があり、それをアルコニックスグループや社会に示していくことが使命のひとつ。
部門・グループ会社横断での取組みを行うCVCの活動は、グループのパーパス・ビジョンにある「つなぐ」を体現する取り組みと言えます。
次回、CVCの投資先の1社であるノベルクリスタルテクノロジー株式会社へのインタビューを通じて、活動の実態に迫ります。